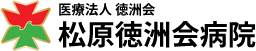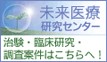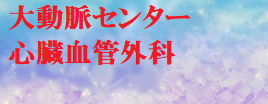臨床試験センター
センター長ご挨拶
治験は、薬の承認を得るために、健康な人や患者さんのご協力をいただいて、有効性や安全性を調べる臨床試験です。「研究」のため、いつもの治療で行わない検査や評価をしたり、来院頻度が増えたりします。
医師から「治験(臨床試験)に参加しませんか」といわれたら、ご家族やかかりつけ医と相談しても構いませんので、あなたの自由意思で決めてください。気になることがあれば、なんでもお尋ねください。
臨床試験センター長 脳神経外科部長 大山 憲治
臨床試験センターの紹介
松原徳洲会病院では2006年10月から治験を実施しています。
治験・臨床研究・製造販売後調査がスムーズに行えるようサポートをしています。
| 資格 |
人数 |
|---|
| 日本臨床薬理学会 認定CRC |
1名 |
|---|
| 日本臨床試験学会 GCPパスポート |
1名 |
|---|
| 日本臨床試験学会 GCPエキスパート |
1名 |
|---|
治験とは
「くすりの候補」が製造販売承認を国に申請するために行う臨床試験を「治験(ちけん)」といいます。
よくある質問
1 治験に参加するためにはどうすればいいですか?
それぞれの治験には、参加できる基準が定められています。それらの基準を満たしている患者さんに、医師より治験のお話をさせて頂きます。
治験への参加は、自由です。お断りになられても、その後の治療で何ら不利益を受けることはありません。
2 治験の参加に同意しても、途中で参加を止めることはできますか?
どのような理由であれ、患者さんの意思が優先されます。
途中で参加をやめられた場合でも何ら不利益になることはありません。
3 安全性については、大丈夫ですか?
治験は厚生労働省の定めた「臨床試験の実施に関する基準」(GCPと呼ばれています)という厳しい規則に則って行われ、患者さんへの倫理的
配慮が最優先されます。治験の途中は、特に副作用に注意が払われ、診察や検査などで頻回に確認を行います。副作用のおそれがあれば適切に治療するとともに、治験を中止するなどの処置が行われ、安全性が確保されるよう配慮しています。治験中、いつもと違う症状が現れた場合はすぐに担当医師にご連絡ください。
4 診察予定日の都合が悪くなった場合、変更できますか?
治験は決められたスケジュールで診察・検査を行いますので、出来る限り予定された来院日に来てください。ただし、都合が悪い場合は事前に治験コーディネーターへご連絡ください。
5 他の医療機関を受診して、もらった薬を使ってもいいですか?
あなたの病気や使用されている薬によっては治験に参加できないことがあります。また、治験期間中は使用できる薬に制限がある場合もあります。そのため、治験に参加を同意される前に、必ず担当医師もしくは治験コーディネーターに、どのような薬を使用されているか伝えてください。また、治験参加中に新たに医療機関を受診される場合、新たに薬(薬局で購入される市販薬)、サプリメント、健康食品などを始める場合は、事前にお知らせください。
治験参加カードなど治験の内容をまとめたカードをお渡しすることがあります。
6 治験の費用について教えてください。
治験薬は無償で提供されます。患者さんを対象とした治験では、交通費等の負担を軽減するために「負担軽減費」をお支払いいたします。月毎にまとめて振り込みでお渡ししています。また、治験期間中(原則、治験薬を使用している期間)の検査の費用は治験を依頼している製薬会社が負担します。よって、治験に参加している間、医療費負担が普段より少なくなることがあります。ただし、治験の対象である病気以外のお薬や初診料・再診料などは通常の保険対象となり、それは患者さんの自己負担となります。
7 健康被害が生じた場合の対応は?
治験に参加したことによって、何らかの健康被害が起こった場合には適切な治療を行います。また、必要に応じて補償が受けられます。ただし、患者さんの故意または重大な過失による場合には補償を受けられない場合があります。それぞれの治験説明時に、医師や治験コーディネーターが詳しくお話しします。
8 プラセボとは何のことですか?
有効成分を含まない飲み薬や注射薬のことをいい、成分を含む薬とは見た目には全く区別がつかないようになっています。
治験には研究的な側面もあり、治験薬の効果を客観的に調べるため、比較する薬としてプラセボが使われる場合があります。治験薬はプラセボと比較してはっきりと上回る効果が認められて、初めて『薬』として認められます。
9 治験に参加するとどんなメリットがありますか?
治験に参加することで得られるメリットはいろいろありますが、代表的なものとしては、「新しい治療を受けるチャンスがあります。」、「経験豊富な担当医師による丁寧な診察が受けられます。」、「一般の診察より詳しい検査が行われます。」という点が上げられます。
10 治験終了後も引き続き治験薬での治療を受けられますか?
治験薬で治療効果が得られても、治験が終わるとその治験薬を続けることは出来ません。非常に重い病気の場合などは、可能なこともありますので、治験の説明の時に確認してください。
実施中の治験(2025年11月時点)
詳しくは臨床試験センターまでお問い合わせください。
ご連絡先 072-334-3400(代表)
お問い合わせ時間:月~土 9:00-17:00
終了した治験(2006年~2024年)
実施中の臨床研究(人を対象とした医学系研究)
詳しくは主治医にご確認ください。臨床試験センターでもお受けします。
072-334-3400(代表)
お問い合わせ時間:月~土 9:00-17:00
治験コーディネーターの業務内容
患者さまが安心して研究に参加できるよう医師・依頼者(製薬会社など)と連携をとります。主な業務内容を図に示します。
当センターの特長
全国の徳洲会グループには約100名のCRCが在籍しています。そこで臨床試験部会を開催し、グループ全体で治験や臨床試験について検討しています。
会議や研修を通じ全国のCRCと交流を深めることができ、気軽に情報共有ができます。ネットワークを活かした運営で救急・入院・外来とあらゆる分野の治験の依頼を受けることができます。
詳しくは徳洲会臨床試験部会をご覧ください。
求人情報
依頼者の方へ